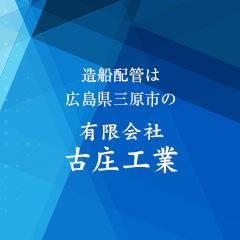-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー

皆さんこんにちは!
有限会社古庄工業、更新担当の中西です。
さて今回は
造船配管は、流体の道を設計し、安全に流し続けるための基幹工事。
燃料・海水・潤滑・空気・計装・冷媒……一本の配管が安全・性能・工期・LCC(ライフサイクルコスト)に直結します。
①一発で付くスプール(設計・製作)
3D干渉の完全解消、**取り合い寸法(面間・ガスケット厚・伸縮代)**の明記。
支持金物・貫通(MCT)・断熱・塗装復旧まで前倒し確定。
②品質と安全の両立(施工)
PTW/LOTO・火気管理・ガス連続監視(狭隘/タンク内)。
WPS/PQR順守、溶接履歴とヒートNo.のトレーサビリティ。
極低温・低引火点燃料(LNG/メタノール/アンモニア/水素)系の二重殻・ベント・パージ。
③クリーンネスと検査(試運転前)
フラッシング流速・ΔP・フィルタメッシュ、NAS/ISO清浄度の達成。
酸洗・パッシベーション、Heリーク/耐圧・気密の一次合格。
④保全性とLCC(運用)
ドレン・ベント・ストレーナ位置、デッドレグ最小化、振動・熱膨張の吸収(ベローズ/ループ)。
⑤生産性とデジタル(全体)
スプール化・キッティング・オービタル溶接でタクト短縮。
QR台帳(材質・溶接・検査・塗装・断熱)でクラス査察即応。
“流れ出す瞬間”に立ち会える:フラッシング完了→ポンプ始動→圧・流量が狙い値に乗る高揚。
手仕事×エンジニアリングの融合:現合ゼロで納まる曲げ、オービタルのビードが揃う快感。
制約を解くパズル:狭い艤装空間で安全・点検性・工程を同時に満たす設計解。
安全と命を守る誇り:漏れない=燃えないを実装し、海上試運転を支える中核。
チームの一体感:船殻・機械・電装・塗装が一本の配管でつながる達成感。
“一発取付”達成:3D点群→先行製作→現場Fit-up無手直し。再溶接ゼロ・工程1日短縮。
Heリーク一次合格:燃料ガス系で0件是正、ガス供給の立上げが予定前倒しに。
海水系の材質見直し:一部をGREへ→腐食トラブル激減、保守停止も短縮。
QR台帳導入:溶接・検査・塗装が即参照でき、クラス指摘ゼロ更新。
図面に赤で“圧力境界&清浄度境界”を明示:フラッシング対象が一目で。
スプール毎に“取り合い寸法ラベル”:面間・ガスケット厚・許容差を現場で即確認。
Fit-up三点セット:芯出し→回転角→銘板/ヒートNo.撮影を溶接前チェックに。
フラッシングは“逆流→順流”:デッドレグ洗浄と粒子カウンタ記録をセットで。
極低温支持の見える化:コールドシュー位置・熱橋・結露ラインを断面スケッチで共有。
MCTマトリクス:径・本数・ブロック・優先度で貫通の先行固定。
10分クラッシュ・ハドル:船殻/配管/電装/塗装の立会いで**“今日の干渉”を朝解決**。
スプール一次合格率(%)/現場切回し率(↓)
RT/UT不合格率(ppm)/溶接是正率(%)
耐圧・気密・Heリーク一次合格率(%)
清浄度合格率(NAS/ISO)/フラッシング回数
再作業人時/スプール/工程遵守率
安全:ガス測定逸脱ゼロ継続日数/Stop Work発動件数(↑は健全)
査察:クラス指摘件数/トレーサビリティ完備率(%)
大切なのは他社比較より自ラインの基準線を上げ続けること。設計→製作→施工→検査→運用のPDCAが王道です。
安全:狭隘・高所・火気のPTW/LOTO、換気・連続ガス監視、火花看視の二重化。
身体:頭上・前屈姿勢を減らす治具・昇降台・支持スタンド、重量物は押す>持つへ。
学び:IGF/代替燃料、オービタル、清浄度規格、HAZOPの基礎。
文化:誰でも作業停止を宣言できるStop Work権限の明文化。
製作工 → 取付工 → 溶接管理/班長 → 施工管理 → QA/QC・検査 → 試運転 → 配管設計(3D)/計画 → PM。
横断スキル:配管クラス、材料・腐食、NDT、清浄度、3D/アイソメ、工程・安全、英語・クラス対応。
代替燃料フル対応:メタノール・アンモニア・水素で材質・ガス検知・換気が再定義。
モジュール&スキッド:FGSSやユーティリティの**“据えてつなぐ”**化。
自動化・ロボ:小型ロボFit-up、オービタル常用、パイプショップの自動切断・マーキング。
デジタルスレッド:設計→製作→検査→引渡しのQR台帳一気通貫。
CBM×設計リターン:実船の圧・温・振動ログを次船の配管クラスへ反映。
造船配管のニーズは、一発で付くスプール/安全と清浄度の証跡/極低温・代替燃料対応/トレーサビリティと生産性。
その中でのやりがいは、流れを生み出す瞬間に立ち会えること、手仕事と工学を融合して最適解を形にすること、安全と性能で船を支える誇りにあります。
“漏らさない・燃やさない・止めない。”
今日の一本が、明日の航海を強くします。
有限会社古庄工業では、一緒に船舶の安全運航を支える仲間を募集中です!
「人柄」を最重視する採用方針で、未経験の方も大歓迎。
詳しくは求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
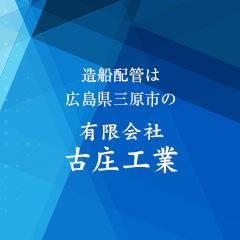
皆さんこんにちは!
有限会社古庄工業、更新担当の中西です。
さて今回は
設計:テンプレートと手描き図、現場採寸→**現合(げんごう)**で取り回すのが常態。
製作:単純ベンダ・ロールでの曲げ、継手は手溶接中心。
材料:軟鋼・CuNi(90/10)・黄銅・黒ガス管、海水系はCuNiが主流。
品質:漏れ試験・通水試験は現場仕上げ後に実施。職人の勘が品質を左右。
設計の標準化:系統ごとに**配管クラス(圧力・温度・材質・継手規格)**を整備。
スプール化:**アイソメ図(スプール図)**で工場先行製作→現場は取り付け主体へ。
NC化:NCパイプベンダ・パイプ切断機の普及で曲げ精度と歩留まりが向上。
検査:PN・Classごとの耐圧/気密が体系化、NDT(PT/MT/RT/UT)を組み合わせる文化に。
3D CAD/PDMSの導入で干渉チェック・重量・MTOが前倒し可能に。
ブロック艤装:船殻ブロック段階で**配管・支持金物・貫通部(MCT)**を先付け、進水後の工数を圧縮。
材料の多様化:**ステンレス(316L)・二相系・GRE(海水系)**の使い分けが一般化。
品質・安全:A60/Hクラス隔壁の耐火貫通・防火塗装・コーティングの整合が標準に。
LNG船・FGSSの普及で**極低温(-162℃)**配管・バルブ・クライオサポートが主戦場に。
IGFに準拠した低引火点燃料(LNG等)で**二重殻・ベント・パージ(N₂)**の手順が厳密化。
洗浄レベルの高度化:フラッシング・ピックリング・パッシベーションの手順書化、NAS/ISO清浄度管理。
軸系・機関まわり:振動・熱膨張を見込んだベローズ・ループ・フレキ計画が当たり前に。
燃料転換:メタノール・アンモニア・水素対応の配管・材料・検知・換気がテーマ。腐食・脆化・毒性を考慮した材質・パッキン・シールの選定が肝。
デジタルスレッド:3D→スプール→QR→出荷→取付→検査→試運転までをデータ連携、クラウド台帳でトレーサビリティ確保。
製作自動化:レーザーマーキング、自動溶接(TIG/オービタル)、ロボFit-up、ARでの現場照合。
実船フィードバック:I0T圧力・温度・振動で劣化傾向を把握、改修デザインに反映。
複合材・断熱:GRE・サンドイッチ断熱、**極低温支持(G10/マイナス用PU)**や結露対策の標準化。
設計:手描き→2D CAD→3D/干渉自動検出→点群リバースエンジニアリング
材料:軟鋼・CuNi→SUS/二相系・GRE・低温用Ni鋼→代替燃料向け特殊材料
製作:現場現合→工場スプール化→NC/自動溶接・キッティング
施工:後艤装→ブロック先行艤装→AR照合・デジタル出面
検査:通水→耐圧/気密+NDT→清浄度・脱脂・リーク(He)
運用:定期補修→状態基準保全(CBM)→実運用データで設計に戻す
〜1980s:現合・手描き、職人技が中核
1990s:配管クラス整備・スプール化・NC曲げ
2000s:3D設計・ブロック艤装・材料多様化
2010s:LNG/極低温・洗浄レベル高度化・IGF対応
2020s–:代替燃料・DX・自動化・CBM
一発で付くスプール:寸法公差・装備干渉・支持金物まで3DでFIX、現場切り回しゼロへ。
清浄度と脱脂:燃料・作動油・計装系はNAS/ISO規格準拠、フェライト抜きや酸洗・パスの証跡。
極低温・毒性対応:ベント・パージ・検知・換気を含むシステムで安全性を担保。
トレーサビリティ:ヒートNo.・WPS/PQR・溶接者ID・検査結果をQRひも付け。
レイバーセーフティ:狭隘・高所・火気のPTW/LOTOと可燃性ガスの連続監視。
LCC/耐食:海水→GRE・CuNi・SUSの適材配置、蒸気・凝縮水・ケミカルも腐食設計で。
赤ペンで“支持ライン”を先に引く:配管だけでなく支持金物→溶接順序→塗装復旧まで先出し。
スプールには“取り合い寸法”を印字:ガスケット厚・面間・伸縮代を現場が即判断できるように。
洗浄・フラッシングは“逆流→順流”:デッドレグを洗い切る回路図を作ってから着手。
リーク試験の温度補正:気密は温度ドリフトを見込んだ保持時間設定で誤判定を防止。
貫通部は“耐火×気密×防水”の三位一体:MCT・シール材・コーキングの組合せ台帳を標準化。
曲げVS継手の最適解:溶接本数削減=品質と工数の両得。曲げ許容と治具有無で設計段階に判断。
極低温支持は“熱橋・結露”を絵に:断熱の切れ目・吊金具の冷輻射を断面スケッチで共有。
スプール一次合格率(%)/現場合わせ率(↓ほど良)
溶接手直し率(%)/RT/UT不合格率(ppm)
耐圧・気密一次合格率(%)/リーク再試験件数
洗浄・清浄度合格率(%)(NAS/ISO)/脱脂確認の是正率
取付工数(人時/スプール)/工程遵守率
安全:ヒヤリハット報告率(高いほど学習文化)/火気作業違反ゼロ継続日数
重要なのは“他社比較”より自ラインの基準線を上げ続けること。設計→製作→施工→検査→運用のPDCAが王道です。
代替燃料対応の本格化:メタノール・アンモニア・水素で材料・シール・検知が再定義。
デジタルスレッド:PLM/ERPと連携し、材料→加工→検査→引渡しの一気通貫トレース。
自動溶接・自動組立:狭隘域向けの小型ロボ/オービタルの標準搭載。
モジュール&スキッド:FGSS・ユーティリティをパッケージ化し、艤装は**“据えてつなぐ”**へ。
CBM×設計リターン:実船データで振動・腐食・熱膨張の弱点を特定→次船の配管クラスへ反映。
造船配管は、
現合と手描き → 標準化・スプール化 → 3Dとブロック艤装 → 極低温・クリーン・IGF対応 → 代替燃料×DX×自動化
と進化してきました。
これから選ばれるのは、一発で付くスプールと清浄度・安全の証跡、そしてデータで回す改良力を兼ね備えたチーム。
**“漏らさない・燃やさない・止めない”**を合言葉に、次の艦(ふね)をより強く、より賢く。
有限会社古庄工業では、一緒に船舶の安全運航を支える仲間を募集中です!
「人柄」を最重視する採用方針で、未経験の方も大歓迎。
詳しくは求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!